三好のスゴさを体験しよう!
徳島県内の観光名所としても有名なかずら橋や古くから伝承されてきた妖怪伝説はこの地が非常に急峻で険しいところであったことと大いに関係しています。さらに、徳島県民にとって欠かせない吉野川との歴史は深く、人々の暮らしに大きな影響を与えてきました。そんな三好地域をつくっている様々な自然の営みや暮らしてきた人々の知恵と工夫を是非体験しませんか?

SCROLL
「動く大地が創った、
空へとつづく集落と吉野川の流れ」
What’s Miyoshi Geopark Project?
徳島県の西の端にある三好ジオパーク構想エリア。ここには、山の斜面に点在する「傾斜地集落」、四国三郎暴れ川の名を持つ「吉野川」など不思議でステキな風景がたくさんあります。
…どうしてこんな風景が生まれたんでしょう?
不思議でステキな風景の成り立ちを探っていくと、「動く大地」が関係しています。三好ジオパークの「動く大地」について、一緒に探りましょう!

標高1000~2000m級の山々からなる四国山地、剣山を筆頭にそびえ立つ山々の中にある秘境の郷「祖谷(いや)」。何人も寄せ付けない、断崖絶壁の旧街道「大歩危小歩危(おおぼけこぼけ)」そして徳島県民のソウルリバー「吉野川」まで色濃い文化と風景が溢れる地「三好ジオパーク構想」をご紹介します。
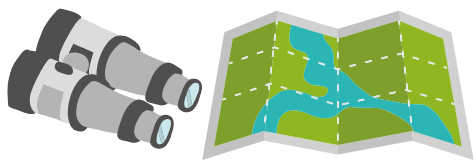


徳島県内の観光名所としても有名なかずら橋や古くから伝承されてきた妖怪伝説はこの地が非常に急峻で険しいところであったことと大いに関係しています。さらに、徳島県民にとって欠かせない吉野川との歴史は深く、人々の暮らしに大きな影響を与えてきました。そんな三好地域をつくっている様々な自然の営みや暮らしてきた人々の知恵と工夫を是非体験しませんか?

三好地域は四国の中心にあることから「四国のへそ」と呼ばれております。そのため、徳島はもちろん、香川、愛媛、高知へのアクセスがしやすいのも地域の特徴です。

